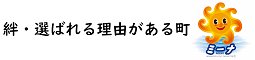住民税の概要
住民税と納税義務者
住民税(町民税と県民税を合わせた呼び方です。)は、一定の額を負担する均等割と所得金額に応じて負担する所得割によって構成され、原則、町内に住所があり、前年中に所得があった人が納税義務者となります。
※町内外へ転入出された場合は、毎年1月1日現在の住所地で課税されます。
このほか、町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する人で町内に住所を有しない人も対象となります。
住民税額の計算方法
住民税額=所得割額+均等割額
- 所得割額=課税所得金額×税率-税額控除
- 課税所得金額=所得金額-所得控除
納付方法
住民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類あります。
会社へお勤めの方は原則特別徴収となります。
それ以外の方は、普通徴収となります。
所得金額
収入金額からいわゆる必要経費を差し引いた額のことをいいます。
給与所得、雑所得(公的年金等、その他)、事業所得(営業等、農業)、不動産所得、一時所得、配当所得、譲渡所得、利子所得、退職所得、山林所得の10種類に分類されています。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されます。例えば令和6年度の住民税では、令和5年中の所得金額が基準となります。
所得控除
配偶者や扶養親族の有無、医療による出費等個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引かれる金額のことで、次のとおりです。
| 種類 | 簡単な説明 |
|---|---|
| 雑損控除 | 災害や、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合 |
| 医療費控除 | 1年間に支払った医療費が、一定額以上ある場合 |
| 社会保険料控除 | 国民健康保険税や国民年金保険料、介護保険料などの支払いがある場合 |
| 小規模共済等共済掛金控除 | 小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払いがある場合 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料や個人年金保険料の支払いがある場合 |
| 地震保険料控除 | 長期損害保険料や地震保険料の支払いがある場合 |
| 寄付金控除 | 国、地方公共団体などに支出した寄付金がある場合 |
| 障害者控除 | あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合 |
| 寡婦控除 | あなたの合計所得金額が500万円以下で、あなたが寡婦である場合 |
|
ひとり親控除 |
あなたの合計所得金額が500万円以下で、あなたがひとり親である場合 |
| 勤労学生控除 | あなたが勤労学生である場合 |
| 配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる場合 |
| 配偶者特別控除 | あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額48万円を越え、133万円未満である場合 |
| 扶養控除 | 扶養親族がいる場合 |
| 基礎控除 |
あなたの前年における合計所得金額が2,500万円以下である場合 |
医療費控除
本人及び生計同一の親族ために一定額以上の医療費の支出があるときの控除です。
申告の際には「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。
控除額
次のとおり計算します。
支払った医療費-保険金等で補てんされる額-「10万円」または「総所得金額×5%」とのいずれか少ない金額
医療費控除の計算例
「支払った医療費の合計」が320,000円、「保険金等で補てんされる額」が162,000円、「総所得金額等」3,677,600円の場合
- 320,000円 - 162,000円 = 158,000円
- 3,677,600円×0.05=183,880円
- 183,880円>100,000円 → 100,000円
- 158,000円 - 100,000円=58,000円
医療費控除の金額は、58,000円になります。
社会保険料控除
あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などで、あなたが支払ったり、給与や年金から差し引かれた保険料がある場合の控除です。
申告の際には各種納付証明書の添付が必要です。
生命保険料控除(証明書添付)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 12,001円から32,000円まで | (支払った保険料)×1/2+6,000円 |
| 32,001円から56,000円まで | (支払った保険料)×1/4+14,000円 |
| 56,001円以上 | 一律に28,000円 |
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 15,001円から40,000円まで | (支払った保険料)×1/2+7,500円 |
| 40,001円から70,000円まで | (支払った保険料)×1/4+17,500円 |
| 70,001円以上 | 一律に35,000円 |
| 適用する生命保険料控除 | 控除額 |
|---|---|
| 新契約のみ生命保険料控除を適用 | 1に基づき算定した控除額 |
| 旧契約のみ生命保険料控除を適用 | 1に基づき算定した控除額 |
| 新契約と旧契約の双方について 生命保険料控除を適用 |
1に基づき算定した新契約の控除額と 2に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円) |
4.生命保険料控除額
1~3による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が70,000円を超える場合には、生命保険料控除額は70,000円となります。
地震保険料控除
長期損害保険や地震保険などの保険料を支払った場合の控除です。
長期損害保険料とは保険期間や共済期間が10年以上の契約で、保険料期間が終了したときに満期返戻金が支払われる旨の特約があるものなどに係る損害保険料や掛金をいいます。
※一つの損害保険契約の中で地震保険分と長期損害保険分がある場合は、どちらか一方のみが該当となります。
保険区分
| 保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払った保険料の全額×0.5 |
| 50,001円以上 | 一律に25,000円 |
保険区分
| 保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 5,001円~15,000円 | 支払った保険料の全額×0.5+2,500円 |
| 15,001円以上 | 一律に10,000円 |
保険区分 3.地震保険契約と損害保険契約との両方の保険料の場合
1、2でそれぞれ計算した金額の合計額(最高限度25,000円)
障害者控除
あなたや控除対象配偶者、扶養親族に障害がある場合の控除です。
障害者とは、身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳、戦傷病者手帳などをもらっている方や、精神または身体に障害のある65才以上の方でその障害の程度が障害者手帳交付者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方などです。
障害者控除額
1人につき26万円です。
なお、次に該当する方は、特別障害者として、30万円の控除が受けられます。
- 身体障害者手帳1級及び2級程度
- 精神障害保健福祉手帳1級
- 療育手帳A判定
- いつも病床にいて複雑な介護を必要とする方(介護保険認定者の障害者控除対象者認定書が必要)
寡婦控除
夫と死別した後再婚していない方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方が受けられる控除です。
寡婦控除金額
控除額は26万円です。
ひとり親控除
前年の合計所得が500万円以下の方のうち、婚姻歴や性別にかかわらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する単身者の方が受けられる控除です。
ひとり親控除金額
控除額は30万円です。
配偶者(特別)控除
あなたに生計を一にする配偶者がいる場合に、あなたと配偶者の令和5年分の合計所得金額に応じて受けられる控除です。
| 配偶者の合計所得金額 | あなた(居住者)の合計所得金額 900万円以下 |
あなた(居住者)の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
あなた(居住者)の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
控除の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 配偶者控除 |
| 老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 配偶者控除 |
| 48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 配偶者特別控除 |
| 95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 配偶者特別控除 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 配偶者特別控除 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 配偶者特別控除 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 配偶者特別控除 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 配偶者特別控除 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 配偶者特別控除 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 配偶者特別控除 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 配偶者特別控除 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 配偶者特別控除 |
あなたの令和5年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
扶養控除
あなたが、生計を一にする合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する場合の控除です。
| 種別 | 区分 | 扶養控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 通常 | 33万円 |
| 一般の扶養親族 | 同居特別障害者 | 56万円 |
| 特定扶養親族(19才以上~23才未満) | 通常 | 45万円 |
| 特定扶養親族(19才以上~23才未満) | 同居特別障害者 | 68万円 |
| 老人扶養親族(70才以上) | 通常(同居老親以外) | 38万円 |
| 老人扶養親族(70才以上) | 通常(同居老親) | 45万円 |
| 老人扶養親族(70才以上) | 障害者(同居老親以外) | 61万円 |
| 老人扶養親族(70才以上) | 障害者(同居老親) | 68万円 |
雑損控除
あなたや扶養親族が、災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。
控除額
次のいずれか多い金額
- (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の10分の1)
- (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
寄附金控除
都道府県、市町村、住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対して寄附金を支出した場合につき次のいずれか低い方の金額の10%が住民税額から控除されます。
控除額
次のとおり計算します。
- (寄附金の合計金額-2千円
- 総所得金額等×30%-2千円
※ふるさと納税についての詳細は、寄附金税制の拡充(ふるさと寄附金納税に関する個人住民税の控除)のページをご覧ください。
勤労学生控除
あなたが学生、生徒又は児童で、自己の勤労に基づいて得た所得が75万円以下であり、不労所得が10万円以下である場合に受けられる控除です。
控除額
26万円です。
基礎控除
基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の方が受けられる控除です。
控除額
合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円超の場合は適用外とされます
|
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用外 |
課税所得金額
所得金額の合計から所得控除を引いた金額です。
1,000円未満を切り捨てます。
均等割
年額で
- 県民税・・・1,500円
- 町民税・・・3,000円
- 森林環境税(国税)・・・1,000円
※「森林環境税」は令和6年度から、個人住民税の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課 徴収するものです。
ただし、一定基準に該当する方は課税されません。
課税されない方については、本ページ下部にある「課税されない方」の項をご覧ください。
所得割の税率
課税標準額に税率を掛けて求めた金額になります。
税率は一律10%(町民税6%、県民税4%)です。
ただし、一定基準に該当する方は課税されません。
課税されない方については、本ページ下部にある「課税されない方」の項をご覧ください。
(注)分離課税の所得がある場合は異なります。(分離課税の税率)
| 区分 | 町民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得(分離短期一般) | 5.40% | 3.60% |
| 短期譲渡所得(分離短期軽減) | 3% | 2% |
| 長期譲渡所得(分離長期一般) | 3% | 2% |
| 長期譲渡所得(分離長期特定)[2,000万円以下の部分] | 2.40% | 1.60% |
| 長期譲渡所得(分離長期特定)[2,000万円超の部分] | 3% | 2% |
| 長期譲渡所得(分離長期軽課)[6,000万円以下の部分] | 2.40% | 1.60% |
| 長期譲渡所得(分離長期軽課)[6,000万円超の部分] | 3% | 2% |
| 株式等に係る譲渡所得等(未公開分) | 3% | 2% |
| 株式等に係る譲渡所得等(上場分) | 3% | 2% |
| 先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% |
税額控除
配当控除年額
配当控除の対象となる一定の配当所得がある場合、その年分の住民税所得割額から一定額を差し引きます。
| 課税所得金額 | 1,000万円以下の部分(町民税) | 1,000万円以下の部分(県民税) | 1,000万円超の部分(町民税) | 1,000万円超の部分(県民税) |
|---|---|---|---|---|
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 証券投資信託等 (外貨建等証券投資信託以外) |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 証券投資信託等 (外貨建等証券投資信託) |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得や、配当の支払いの際に源泉徴収される一定の上場株式等の配当等の所得については、県民税株式等譲渡所得割または県民税配当割として町民税1.8%、県民税1.2%の税率による分離課税が行われます。
この所得については申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は個人住民税所得割で課税されますので、二重課税とならないよう株式等譲渡所得割額または配当割額相当額が控除されます。
住宅借入金等特別控除
個人が、国内において一定の要件に当てはまる居住用家屋の新築、購入又は増改築等をして、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに間に入居し(その新築又は購入の日から6カ月以内に入居した場合に限ります。)、居住日以後その年の12月31日まで、引き続き自己の居住の用に供している場合において、その住宅の取得等のための一定の借入金等を有する場合には、その家屋に入居し又は増改築等をした部分を居住の用に供した日の属する年分以後10年間の各年の所得税の額から一定の方法で計算した住宅借入金等特別控除額の控除を受けることができます。
調整控除
税額移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除します。これを調整控除といいます。
※人的控除は基礎控除のみとする。
調整控除の計算
課税所得金額が200万円以下の場合
「人的控除の差の合計額」と「課税所得金額」のいずれか小さい額の5%
課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
|
控除の種類 |
納税義務者の合計所得金額 |
||
|---|---|---|---|
|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
|
配偶者控除(一般) |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
|
配偶者控除(老人(70才以上)) |
10万円 |
6万円 |
3万円 |
|
配偶者特別控除(48万円超50 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
| 配偶者特別控除(50万円以上 55万円未満) |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
|
控除の種類 |
人的控除額の差 |
|---|---|
| 障害者控除(普通) |
1万円 |
| 障害者控除(特別) |
10万円 |
| 同居特別障害者 |
22万円 |
| ひとり親控除(母) |
5万円 |
| ひとり親控除(父) |
1万円 |
| 寡婦控除 |
1万円 |
| 勤労学生控除 |
1万円 |
| 扶養控除(一般扶養) |
5万円 |
| 扶養控除(特定扶養) |
18万円 |
| 扶養控除(老人扶養) |
10万円 |
| 扶養控除(同居老親) |
13万円 |
| 基礎控除 |
5万円 |
課税されない方
均等割も所得割も課税されない方
- 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人。
- 障害者、未成年者(1月1日現在において20才以下で、婚姻していない人)、または寡婦・寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の人。
均等割がかからない方
- 前年中の合計所得金額が、下記の金額以下の人
扶養親族がいる方 ・・・28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円
扶養親族がいない方・・・38万円
所得割がかからない方
- 前年の総所得金額等(※1)が、下記の金額以下の人。
扶養親族がいる方 ・・・(扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円
扶養親族がいない方・・・45万円
※1 前年の総所得金額等
損益通算及び損失の繰越控除を適用した後の総所得金額と分離課税の所得金額(土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額)の合計額をいいます。
町県民税の特別徴収(給与からの天引きによる納付)とは
会社へお勤めの方(給与所得者)は、納税の便宜を図る目的から、1年間に納入しなければならない町県民税を12回に分割して6月から翌年5月(税額が5,500円以下の人については、その全額を最初の月)まで毎月給与の支払われるときに勤務先事業所が差し引いて納税する制度です。
詳しくは個人住民税の特別徴収の推進ページをご覧ください。
普通徴収とは
事業所得者、公的年金受給者等の給与所得者以外の人は、納税通知書または口座振替により、年4回の納期に分けて納税することになります。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期分 | 6月末日 |
| 第2期分 | 8月末日 |
| 第3期分 | 10月末日 |
| 第4期分 | 12月25日 |
関連ページ
減免制度
納税者が生活保護を受けることになったり、前年中の所得が一定条件に当てはまる方が長期療養、失業等により著しく所得の減少が見込まれることとなり、納税が困難なときには、申請により減免が受けられます。
減免申請の手続きは
減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに印鑑と納付書および必要書類を持参の上「減免申請書」を提出してください。この制度は納税が困難な方を対象としておりますので、申請は納付の前に限られます。納付後の申請はできませんので、ご注意ください。
町民税を減免する必要があると認められる者
- 生活保護法の規定による保護を受けることになった者
- 賦課期日後に死亡した者のうち前年中における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(合計所得金額)が210万円以下の者
- 長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上の療養を擁すると思われる者をいう。)で前年中の合計所得金額が210万円以下の者
- 賦課期日現在において勤労学生であり前年中の所得金額が基礎控除以下の者
- 雇用保険法の規定によって、基本手当の受給資格を有する者で前年中における合計所得金額が210万円以下の者
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。