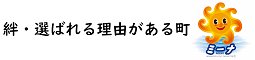国指定文化財
羽豆神社の社叢(はずじんじゃのしゃそう)
- 種別
- 天然記念物
- 指定年月日
- 昭和9年1月22日
- 数量
- 12,980平方メートル
- 所在地
- 南知多町大字師崎字明神山2番地他
- 所有者
- 羽豆神社

指定されているのは、知多半島の最先端羽豆岬一帯で、建稲種命を祀る式内社羽豆神社の社叢です。昭和8年頃の調査によると、波打ち寄せる海岸にはハマナデシコ、ハマキケマン、ハマツナギ、ハマアカザなどが、崖にはウバメガシ、トベラ、イヌビワ、マサキなどが密生し、社叢にはウバメガシの大木がいたるところにみられ、原生林のようであったといいます。昭和34年の伊勢湾台風で大木のほとんどが倒れるなど大きな被害を受けましたが、ウバメガシを中心に回復し、イブキ、トベラ、ヤブニッケイ、モチキなどが共存する暖地性常緑樹林となっています。
大蔵経(一切経)(だいぞうきょう(いっさいきょう))
- 種別
- 書籍
- 時代
- 鎌倉時代
- 指定年月日
- 昭和14年5月27日指定
- 数量
- 5,463帖
- 所在地
- 南知多町大字山海字間草117番地
- 所有者
- 岩屋寺

宋の淳祐10年(1250)に刊行されたもので、宋版5,157帖と和版111帖、写本195帖、合わせて5,463帖です。経本は2帙ずつ188合の箱に納められて、欠本が少なくよく完備していることで知られています。これらは、宝徳3年(1451)9月、大野城主佐治盛光が岩屋寺へ寄進したものといわれ、宝徳三年目録2帖、目録残巻1巻、千賀重親筆書状1通、智峰筆修補大蔵経願文1通とともに国指定文化財に指定されています。
金銅法具類(こんどうほうぐるい)
- 種別
- 工芸
- 時代
- 鎌倉時代
- 指定年月日
- 昭和14年9月8日指定
- 数量
- 五鈷杵1柄、五鈷鈴1口、金剛盤1面、火舎1口、花瓶2口、灑水器1口、塗香器1口、飲食器1口、六器6口
- 所在地
- 南知多町大字山海字間草117番地
- 所有者
- 岩屋寺

寺伝によると、弘法大師が入唐のおり願って持ち帰った法具で、大同3年(808) 奥之院を開いた際の仏事に用いられたものとされています。指定されているのは、金剛盤とその上に置かれた五鈷鈴、五鈷杵、火舎(香炉)、花瓶(花を供える壺で2口)、灑水器(香水を入れる器)、塗香器(香の容器)、飲食器(食物を盛る器)、六器(水や香などを盛る鋺で6口)です。五鈷鈴の脇鈷(もり)の鋭さやそれぞれの法具にみられる端正な作りなどから、鎌倉時代の前半に制作されたものと考えられています。
尾州廻船内海船船主 内田佐七家(旧内田家住宅)(びしゅうかいせんうつみぶねふなぬし うちださしちけ(きゅううちだけじゅうたく))
- 種別
- 建造物
- 時代
- 明治時代
- 指定年月日
- 平成29年7月31日指定
- 数量
- 13棟
- 所在地
- 南知多町大字内海字南側39番地
- 所有者
- 南知多町

内海を代表する有力船主であった2代目内田佐七による建造物で、棟札や古図などから明治2年(1869)に竣工したことが確認できます。主屋・座敷・いんきょ・新納屋及び複数の小屋と蔵から構成されており、太平洋側に現存する廻船主の家屋の中では大規模なものです。平成20年3月に町文化財に指定され、平成29年7月に国の重要文化財建造物となりました。現在、登録有形文化財建造物である「旧内田佐平二家住宅」と合わせて、土曜日・日曜日および祝日に一般公開を行なっています。(詳細は「尾州廻船内海船船主 内田家」のページをご覧ください。)
このページに関するお問い合わせ
教育課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。