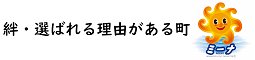地震への備え
地震が起きたときの心得10ヶ条
- まず、わが身の安全を
大きな揺れは1~2分、机やベッドの下などで身の安全を図りましょう。 - すばやく火のしまつを
あわてず、冷静に、ガス機具等の火をけしましょう。 - 火が出たら、まず消火
万一出火したら、消火器やバケツで初期消火。隣近所みんなで協力して火を消しましょう。 - あわてて外にとびだすと危険
あわてて外へ出ると、瓦やガラス、看板などで思わぬケガをすることがあります。ヘルメットや防災頭巾をかぶりましょう。 - 狭い路地、塀ぎわ、崖、川べりに近寄るな
狭いところでは、瓦などが落ちてきたり、ブロック塀が倒れてきたりします。崖や川べりは崩れやすくなっていることが多いので気をつけましょう。 - 津波、浸水、山崩れ、崖崩れに注意
津波、山崩れ危険地域の人は、近くの山や安全な場所へ避難しましょう。 - 避難は徒歩で、持ち物は最小限に
車での避難は、消火、救急活動のさまたげになります。持ち物は最小限にとどめて、身軽に行動できるよう心がけましょう。 - 協力しあって応急救護
災害が大きくなると、負傷者の数も多くなります。軽いケガなどの処置は、みんなで協力しあって応急救護をしましょう。 - 正しい情報をつかみ、デマにまどわされるな
一般に余震は本震よりも小さく、回数が多いのが特徴です。余震には十分に注意し、町の広報、CATVやオフトーク、テレビ、ラジオなどの情報に気をつけ、デマにまどわされないようにしましょう。 - 秩序を守り、自主防災組織等に協力
避難地では、町・自主防災組織等の指示に従って行動しましょう。
日ごろの家庭での地震対策
地震による被害、特に死傷者などの人的被害を少なくするためには、日ごろから対策をたて、すぐ行動できるようにしておくことが大切です。
- 家具の転倒防止・落下物対策
どんなに建物を丈夫にしても、タンスや食器棚が倒れてきてケガをしては何もなりません。倒れそうな家具はしっかり止め、家族からケガ人を出さないようにしましょう。 - 火災防止対策
地震が起きたら、まず身の安全を確保し、次に火を消しガスの元栓を閉めましょう。火災は出して消すよりも出さないことです。日ごろから火を使うところには消火器や消火用の水を用意し、万一火が出てもすぐ消せる準備をしておきましょう。また、防災訓練などで、消火器の使い方を身につけておくことが必要です。 - ブロック塀・門柱の点検および改善
ブロック塀や門柱は、見かけはしっかりしていても、鉄筋が入っていないものなど安全性に欠けるものがたくさんあります。 - 医薬品の準備と救護知識の習得
大地震が発生した場合、ケガをしても病院で直ちに治療を受けることは困難です。いざという時に備え、各家庭では救護薬品などの準備をするとともに、三角巾の使い方など簡単な救急法を身につけておきましょう。 - 食料・飲料水の準備
突然地震が起きて、食料のたくわえが全くなかったら…。たとえお金があっても食料品やスーパーマーケットで買うことはできません。また、地震が起きた直後は、食料輸送も満足にできません。救護活動が受けられるまでの間の食料は、各家庭でたくわえておく必要があります。 - 非常持出品
非常持出品は、家族構成を考えて必要最小限度のものを用意しておきましょう。 - 防災訓練への参加と家庭での役割分担
いざという時に、冷静な行動をとるためには、日ごろからの訓練が大切です。地域の防災訓練には、家族ぐるみで積極的に参加しましょう。また、家庭内の地震対策についても、津波・山崩れ危険地域と一般地域の対応の違いを確かめておく必要があります。
このページに関するお問い合わせ
防災交通課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
防災交通課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。