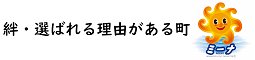内田家について
「尾州廻船内海船船主 内田家」とは
「内田家」とは

「尾州廻船内海船船主内田家(びしゅうかいせんうつみぶねふなぬしうちだけ)」は、内海船を代表する有力船主であった内田佐七(さしち)家によって造られた明治初期の建造物です。
多くの廻船を所有していた内田佐七の家屋「旧内田家住宅」と、その船頭として活躍し、佐七家の娘婿となった人物を初代とする分家の家屋「旧内田佐平二(さへいじ)家住宅」から成っています。
内海船とは
江戸時代、物流の主役は船でした。尾張の国の人が所有する荷物運搬用の大型船を尾州廻船(びしゅうかいせん)といい、このうち内海やその周辺を拠点としたものを内海船(うつみぶね)と呼びました。全盛期には100艘もの船を抱えた巨大集団で、瀬戸内海から江戸にかけて広く活躍しました。
同じ時期の廻船には樽廻船や菱垣廻船などがありますが、積荷の運賃を利益としたそれらの船とは異なり、内海船は生産地で買い取った商品を運んだ先で売却するという「買い積み方式」を取っていました。
また、商人や資本家からもまったく独立していたため、大きな利益を上げました。
旧内田家住宅
旧内田家住宅とは

旧内田家住宅は、平成29年に国の重要文化財に指定された明治初期の建造物です。内海船を代表する有力船主であった2代目内田佐七によって、明治2年(1869)に造られました。
太平洋側に現存する廻船船主の家屋の中でも大規模なもので、当時の船の船材が部分的にではありますが残されています。
旧内田家住宅のつくり
旧内田家住宅は、主屋、座敷、いんきょ、新納屋および複数の小屋と蔵から構成されています。
最も古い主屋・座敷部分は、棟札や古図などから明治2年(1869)に竣工したことが確認できます。
屋敷構えは庄屋格相当の規模と格式を備えており、廻船主の屋敷として数少ない貴重な遺構です。
主屋

日常の生活を送った主な建物です。南北3室、東西2列の六間取(むつまど)りを基本とした造りとなっており、中央奥の部屋が仏間と神屋に分かれているのが特徴です。広く作られた神屋には金刀比羅宮(航海安全)をはじめとした神が祀られており、廻船主の信仰の深さがあらわれています。
「にわ」と呼ばれる土間にはかまどや井戸が設けられ、炊事や仕事場として使われていました。上方には太い梁を組んだ豪快な小屋組が見えており、かまどの煙を外に出したり、明かりを取るための煙出しが設けられています。
座敷

この屋敷で最も格式の高い建物であり、「上の間」「次の間」「茶の間」「奥のこま」から構成されています。内海船船主の組合「戎講(えびすこう)」の寄り合いや、冠婚葬祭など特別な場合に使用されました。
特に「上の間」は、付け書院、床の間、床脇の座敷飾りが設けられ、木目の美しい天井板は屋久杉といわれています。
「茶の間」は三畳三台目(台目:一畳の4分の3)の広さで、窓や天井などに数奇屋造の特徴があらわれています。茶室の機能と同時に、広間の水屋としての機能も備えています。
庭園

この屋敷には座敷「上の間」「次の間」の南側にある主庭、および北側の「茶の間」に面する小庭と主屋の前庭、合計で3つの庭があります。
主庭は張り出した露台を中心に構成されています。端正な手水と石灯籠とが主景を成しており、津藩の藤堂家から贈られた鞍馬石、現在の神奈川県で産出した根府川石をはじめとした、大振りの庭石の力強さも特徴です。対照的に「茶の間」に面した北の小庭は、侘びた雰囲気の落ち着いた造りとなっています。
主屋の前庭は、かつては塀で仕切られた小庭でした。縁の前にある四角の立ち手水は回転する珍しい仕組みになっており、屋敷が使われていた当時は季節に合わせて模様を変え、楽しむことができました。
いんきょ

老夫婦のための別棟の建物です。主屋から少し遅れ、明治5年(1872)に完成しています。
明治7年(1874)には、知多半島で3番目の郵便局である「東端(ひがしばた)郵便取扱所」も開設されました。
1階部分には、内海船でかつて実際に使われていた道具や、船の模型等も展示されています。また、下の紹介映像の完全版も、こちらの建物で常時放映しています。
旧内田佐平二家住宅
旧内田佐平二家住宅とは

旧内田佐平二(さへいじ)家住宅は、平成30年に国の登録有形文化財建造物に登録された明治初期の建造物です。内田佐七家の出店(現三重県津市にあった矢野店)の管理を任されていた初代佐造が内海に帰ってきたときに、その屋敷地として内田佐七家によって建てられました。
明治5年(1872)5月に作成された家相図や家相を占った古文書から、この頃に建設されたことがわかります。
旧内田佐平二家住宅のつくり
旧内田佐平二家住宅は、主屋、土蔵、隠居屋、表門および納屋、透塀から構成されています。
南北に細長い敷地の南辺に表門を構え、その東西に納屋が接続しています。表門を入って正面に主屋が建ち、その北側に土蔵と隠居屋が東西に並んでいます。また、主屋と隠居屋の間の中庭は、透塀で東側隣地と隔てられています。
旧内田家住宅建築時の残材を利用し建築されたともいわれ、間取りなど旧内田家住宅と類似している部分が少なくありません。
主屋

日常の生活を送った主な建物です。南北2室、東西2列の田の字型平面を基本としながら、東列中央に半間幅の廊下状の部屋を設けています。南東部の部屋が9畳床付きの「おでい」で、北面は仏間と神屋に接しています。その北側の部屋は家族の寝所として用いられた「なんど」で、西面には2階へ上がる箱階段があります。また、「なんど」の北側には濡れ縁があり、そこから北に延びる渡り廊下の先に便所が設けられています。2階には前室と主座敷の2部屋があります。
「にわ」と呼ばれる土間にはかまどや井戸が設けられ、炊事や仕事場として使われていました。上方には太い梁を組んだ小屋組が見えており、かまどの煙を外に出したり、明かりを取るための煙出しが設けられています。
隠居屋

隠居屋の東端には吊床の付いた6畳の主座敷があります。南面中央に腰障子が建て込まれ、中庭から直接出入りするようになっています。その西側には下地窓もあり、数寄屋風の意匠になっています。
紹介映像

※完全版の映像(18分程度)は、公開時の内田佐七家「いんきょ」にて常時放映しています。
また、南知多町教育課、町民会館図書室、観光案内所で貸出しも行っています。
ご希望の方は南知多町教育課までお問い合わせください。
お問い合わせ
担当:南知多町教育課
電話番号:0569-65-0711(内線556)
ファクス番号:0569-65-0694
電子メールアドレス:syakyou@town.minamichita.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。